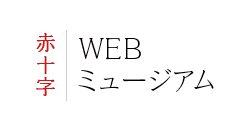特別企画

関東大震災100年 温故備震~ふるきをたずね明日に備える~


1923(大正12)年9月1日、午前11時58分に起きたマグニチュード7.9の大地震は、火災、津波、土石流をともなう未曾有の大災害となりました。かろうじて生き残った人のなかには、火傷や骨折などの重傷者、病人、高齢者、妊産婦、乳幼児など、支援なしで生き延びることが困難な人が少なくありませんでした。
そのときすでに日本赤十字社は、戦時救護のノウハウを活かして自然災害に対応する救護班や救護資機材を整備していました。また、全国の赤十字の支部や病院に加え、活発に活動するボランティアの存在がありました。このような日ごろからの備えと全国的なネットワークが、日赤による関東大震災での救護活動の基盤となったのです。
また国際的には、第一次世界大戦終結の翌1919年に赤十字社連盟が発足し、戦争が終わってもなお苦しむ人々のために平時の赤十字活動を推進することを確認したばかりでした。その4年後に日本で大震災が発生したことを知った世界の赤十字社は、日本を支えるべく立ち上がりました。
日赤の歴史は、救護活動の経験と反省をくり返し、備えを改善してきた歴史でもあります。しかし、どんなに救護活動そのものが進歩したとしても、大災害時に救える命には限りがあります。本特別企画では、「温故知新(おんこちしん)」を言い換え「温故備震(おんこびしん)」と題しました。この言葉には「関東大震災をふりかえることで、明日の災害に備えてほしい」という願いを込めています。
備えることは行動すること。一人ひとりが最善の行動をとるために、先人の取り組みをふりかえります。

関東大震災概要
| 発生年月日 | 1923(大正12)年9月1日 土曜日 午前11時58分 |
|---|---|
| 地震規模 | マグニチュード 7.9 |
| 震源 | 神奈川県西部(相模湾内)、深さ23km |
| 被災地域 | 1府6県(東京府、神奈川県、千葉県、静岡県、埼玉県、山梨県、茨城県) |
| 死者行方不明者 | 約10万5000人 (内) 焼死:約9万2000人 倒壊等:約1万1000人 津波・土砂崩被害:約1000人 地震に伴う事故等:約1500人 |
| 被災人口 | 約340万人 |
| 倒壊・焼失・流出家屋 | 約37万棟 |
| 日赤の活動 | |
| 救護実数 | 56万2381人(延206万7500人) |
| 活動職員総数 | 4466人 |
| 救護機関総数 | 193(救護所、臨時病院、産院など) |
*表は「1923関東大震災報告書第1~3編」(中央防災会議 災害教訓の継承に関する専門調査会、2009年)、『減災と復興 明治村が語る関東大震災』(武村雅之、風媒社、2018)、『日本赤十字社社史稿第4巻』を参考に作成
用語解説
- 赤十字社連盟:現在の国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC)。1919年に発足。各国の赤十字社と赤新月社の国際的連合体で、自然災害時の救護活動や保健・衛生事業の連絡・調整などを行う
- 救護員:戦時並びに自然災害時に救護業務に従事させる者のこと(1923年当時)。医師、看護師、調剤員(薬剤師)、事務職など
- 救護班:救護員のチーム。当時は約20人規模が主で、歯科医、産婆(助産師)などを加えることもできた(2022年現在、救護班編成は6人が基本で、必要に応じ増減できる)
- 救護所:被災現場などで病人やけが人に対して応急的な治療を行う場所
- 救護資機材:医療器具、医薬品、消毒剤、包帯等備品、照明器具、テント、担架、寝具、救護員被服などを指す
- 義捐金:当時、被災者のための寄付金という広い意味で使われていた用語。現在の義援金とは意味合いが異なるため、本企画展では「義捐金」という当時の表記を使用している
注目ポイント
-
 皇居前広場救護所大テントの活動状況
皇居前広場救護所大テントの活動状況
9月1日、午前11時58分に関東大震災が発生。日本赤十字社は、同日夕刻には100坪を超える救護用テントを皇居(宮城)前広場に設置。ただちに傷病者の手当を開始します。
電気やガス、水道も止まり暗闇に閉ざされようとしている皇居前で、赤十字の白いテントだけがランプの光に照らされ、それを目指して焼け出された病人や火傷を負った人々、親を見失った子どもたちが押し寄せてきたのです。このとき広場には30万人の避難者が持ち出した家財とともにひしめきあっていました。
日赤の医師や看護師が治療を行う一方で、水が必要と察知した日赤職員が、4斗樽を持って井戸を往復。避難者は1杯の水を「霊験あらたかな護符」のように受け取ったと言われています。
(日赤の活動は0:30:00あたりから。映像には、1923年当時の救護活動の状況が映し出されますが、そのなかに現在から考えると患者への配慮が欠けているシーンが含まれています。ご了承の上、ご覧ください)
 救護所大テントと赤十字マークのついた救護自動車
救護所大テントと赤十字マークのついた救護自動車
-
 全焼し復興中の日赤本社社屋(博物館明治村所蔵・日本赤十字豊田看護大学管理)
全焼し復興中の日赤本社社屋(博物館明治村所蔵・日本赤十字豊田看護大学管理)
東京・芝区芝公園の日本赤十字社本社(現港区芝大門)は、頑丈な鉄骨レンガ造りで、地震による倒壊をまぬがれました。職員は前庭に救護テントを設置して、集まってきた1000人を超える避難者たちに応急手当を施し、湯茶の提供などを行いました。
しかし9月1日夜半、三方から火焔がせまり、配膳室の窓から火が入り本社ビルは全焼。備蓄していた倉庫内の時価50万円相当の救護資材も燃えつきました。看護師や職員は、避難者を裏門から逃がし、重要書類を携え増上寺付近へと避難しました。
からくも火の手から逃れた職員たちは、豊多摩郡渋谷の日本赤十字社病院(現渋谷区広尾)内に仮事務所を設置。理事会、常議会を開いて、予算500万円を議決し、臨時震災救護部を立ち上げ、救護の手をとめることなく活動を続けました。
 仮設の事務所で業務を行う日赤職員(博物館明治村所蔵・日本赤十字豊田看護大学管理)
仮設の事務所で業務を行う日赤職員(博物館明治村所蔵・日本赤十字豊田看護大学管理)
-
 浅草臨時救護所の石川県支部救護員
浅草臨時救護所の石川県支部救護員
東京や神奈川などの救護班が直ちに活動を開始するなか、翌2日から群馬、栃木、長野、福島、宮城などの支部は応援救護班を被災地に派遣しました。
4日、本社は支部に電報で「成ルヘク多数ノ救護材料ヲ携帯セシメ救護員ヲ派遣セラレタシ」と応援を要請。全国46支部と朝鮮や満州から駆けつけた救護員が、救護所に配備されました。
栃木と長野からの応援が皇居前の救護所に到着したことで、1日から3日間不眠不休の救護活動を続けていた救護員は、ようやく家族を探しに自宅に帰ることができたのです。
最終的に東京では救護所51カ所、巡回救護班4班(内1班は朝鮮支部担当)が稼働しました。東京・神奈川方面の救護所で活動した日赤の救護員は1663人。救護した患者は実人数17万5471人、延人数41万1621人、もっとも長い救護所で翌年1月までの132日間活動しました。
 救護機関配置図(東京)
救護機関配置図(東京)
 救護機関配置図(神奈川)
救護機関配置図(神奈川)
-
 全国救護所配置図
全国救護所配置図
全国に逃れた避難者は約200万人にのぼりました。日赤は、北海道、新潟、大阪、鹿児島など各地の主要駅や港に避難者を受け入れる救護所を73カ所設置。各県、市や青年団、病院などと協力して避難傷病者の救護にあたりました。
地方の救護所を開設したのは32支部、設置期間は平均2~3週間でしたが、長いものは39日という記録があります。医師、看護師、事務員計641名の救護員が救護に従事し、救護患者実数は3万3442人、延人数は5万2963人に達しました。
また、日赤の病院船博愛丸・弘済丸も避難者の輸送にあたりました。鉄道が大きな被害を受けたため、人や物資の輸送に船が大いに活躍したのです。
 東京方面から避難してきた人たちを救護
東京方面から避難してきた人たちを救護
 津波被災者を救護する千葉県支部救護所
津波被災者を救護する千葉県支部救護所
-
 「悪疫予防心得書」
「悪疫予防心得書」
 板橋臨時伝染病院(博物館明治村所蔵・日本赤十字豊田看護大学管理)
板橋臨時伝染病院(博物館明治村所蔵・日本赤十字豊田看護大学管理)
日赤救護班は、感染症流行の兆しを察し、予防と早期発見につとめました。まず患者の受け入れ態勢を整えるため、同じく感染症を警戒した東京府など他機関と連携し、臨時伝染病院を洲崎と板橋に設置、日赤病院は伝染病床を拡張しました。
さらに、爆発的な感染症の拡大を防ぐには人々への注意喚起が必須として「悪疫予防心得書」を30万枚配布しました。結果、東京府下で赤痢2500人、腸チフス3300人余りでくいとめたと記録されています。
「悪疫予防心得書」
伝染病の襲来 大災後の衛生一、水道水のほか生水を飲まぬこと
一、飲み水は必ず煮沸すること
一、腐れかかったもの、未熟の果物不消化のものは食わぬこと
一、大小便は必ず便所にすること
一、食事の前には必ず手を洗うこと
一、熱、下痢、嘔吐のあるものはすぐ医師あるいは救護班にゆくこと
-
 アメリカでの義捐金募集ポスター(東京都復興記念館所蔵)
アメリカでの義捐金募集ポスター(東京都復興記念館所蔵)
震災発生の第一報は、当時日本で唯一海外に打電できる無線局だった福島県磐城国際無線電信局からアメリカに送られ、世界各国に伝わっていきました。
ニューヨークタイムズは「(6年前の)サンフランシスコ地震の際、日本赤十字社は即座に10万ドルを送ってくれた」と紹介。アメリカ赤十字社から同額の緊急義捐金が日本赤十字社に届けられました。
その後、赤十字国際委員会、赤十字社連盟(現国際赤十字・赤新月社連盟)や、アジア、南北アメリカ、ヨーロッパの30カ国近くの赤十字社のほか、各国の団体や個人から義捐金や支援物資が次々と送り届けられました。アメリカ、中国、イタリアなどからは、医師、看護師、建築技術者なども派遣され、被災者の治療、看護、バラック建設などに従事しました。
 イタリア赤十字社寄贈のバラック
イタリア赤十字社寄贈のバラック
 上海紅十字会の救護員(奥)を迎える。米赤Dr. Peters撮影
上海紅十字会の救護員(奥)を迎える。米赤Dr. Peters撮影
-
 震災により生じた地割れの上に建つ麻布臨時病院(テント病院)
震災により生じた地割れの上に建つ麻布臨時病院(テント病院)
震災の報に接したアメリカ大統領で同国赤十字総裁のカルビン・クーリッジは、すぐさま「第一に日本を救え」との命を下しました。フィリピン副総督として赴任の途にあったフランク・アール・マッコイ陸軍少将は、急遽予定を変更して9月6日に来日。アメリカ救護団長兼赤十字代表として、東京・日比谷の帝国ホテル内に事務所を設置し、フィリピンやアメリカから続々と到着する救護資機材、救援物資、人員などの差配に当たりました。資金援助を含め最大の支援国となったのがアメリカでした。
アメリカからの支援の1つである500床規模のテント病院は、麻布の高松宮御用邸内約1万坪の敷地を借り受けて設置。のちに日赤に寄贈され麻布臨時病院として活用されました。この臨時病院は応急救護用に設置されたため、厳冬期に向かうにあたり、寄贈者であるアメリカの同意を得て入院患者を転院させ、テントは他の地域・用途で活用するとして、12月10日に閉鎖しました。
※写真は米赤Dr. Peters 撮影
 東京日比谷・帝国ホテルがアメリカ救護団の拠点となった
東京日比谷・帝国ホテルがアメリカ救護団の拠点となった
 船上にてアメリカ救護団長マッコイ少将(前列中央)
船上にてアメリカ救護団長マッコイ少将(前列中央)
-
 日赤の乳児保護施設
日赤の乳児保護施設
当時、出産は家庭で行うのが習慣であり、産乳児施設はきわめて少なく、震災後に残された東京の施設は東京市1、郡部3、ベッド数わずか83床でした。分娩する場を失った妊婦は、救護テントや路上で出産せざるを得ない状況にあり、受け入れ先を用意することが急務でした。
日赤は病院内の産院を拡張したほか、児童養護施設を運営する福田会などの力を借り、保護者を失った子どもたちのための臨時児童保護施設をつくると同時に大久保や本郷に臨時産院、乳児院を設置しました。
外来で3000人以上の妊産婦を診療し、臨時産院では2151人の妊婦、387人の乳児を保護し、1991人の赤ちゃんが産声をあげました。
また、テントやバラックでの子育ての困難さを鑑み、乳児用の寝床・乳ぐらを考案し、毛布や湯たんぽを添えたセット1万組を被災者に配布。あたたかい心の贈り物として喜ばれました。
 本郷臨時産院で乳児を沐浴
本郷臨時産院で乳児を沐浴
 児童保護施設の子どもたち(博物館明治村所蔵・日本赤十字豊田看護大学管理)
児童保護施設の子どもたち(博物館明治村所蔵・日本赤十字豊田看護大学管理)
-
 乳児の世話をするボランティア
乳児の世話をするボランティア
着の身着のまま大災害から逃れた人々のため、日赤のボランティア組織である篤志看護婦人会は、全国の各支会を動員して衣類5万2696点、慰問袋1万4391個、寄付金437円60銭(当時)を集め、病産院や救護所の被災者に配給しました。少年赤十字(現青少年赤十字)も救護所へ水や食糧の運搬を行うなどの支援活動や、全国規模で募金活動を行いました。
一方、個人からの「何か役に立ちたい」という申し出も多数ありました。震災孤児15人を引きとりたいとの願いが叶わなかった女性に日本赤十字社は、約2カ月間にわたり乳児室で子どもたちの世話をする機会を提供しました。
支援を行う際、もっとも必要なのは被災者のニーズを把握すること。そのうえで、より一層支援の現場でボランティアが力を発揮するためには、被災者のニーズ=needsとボランティアのウォンツ=wants、役立ちたいという気持ちをつなぐことが重要なのです。
*慰問袋 被災者を見舞うため日用品などを袋に詰めたもの
 アメリカ救護団一行を神戸河崎男爵邸内で慰労するボランティア
アメリカ救護団一行を神戸河崎男爵邸内で慰労するボランティア
-
 赤十字マークをつけて復興状況視察団を迎えた震災記念堂
赤十字マークをつけて復興状況視察団を迎えた震災記念堂
震災から11年後、東京で開催された第15回赤十字国際会議の際、被災地の復興状況の視察が行われました。
現地視察では、東京市と日赤がガイドを担い、会議参加者約300名がバス20台に分乗して復興地をめぐりました。1934(昭和9)年10月20日午後2時に日赤本社を出発。ルートは、帝国議事堂(国会議事堂)―青山―表参道―明治神宮―外苑―靖国神社―聖橋―上野公園―浅草―言問橋を通り、4万人以上が火災の犠牲になった本所(現 墨田区)の旧陸軍被服廠跡に建てられた震災記念堂(現 東京都慰霊堂)まで。震災記念堂では、各国の代表らが犠牲者を追悼しました。
東日本大震災時も多くの支援を海外から受けました。そのため2018(平成30)年第3回東日本大震災復興支援国赤十字・赤新月社会議で復興状況を報告し、現地視察の機会を提供するなど、100年前と同様に支援を受けた側の責任を果たすことに尽力しました。
 第15回赤十字国際会議
第15回赤十字国際会議
 日赤産院を視察する会議参加者
日赤産院を視察する会議参加者
-
 赤十字防災セミナー
赤十字防災セミナー
1888(明治21)年磐梯山噴火災害から135年間、日赤は災害救護を行ってきました。その経験の蓄積と教訓は、現在の活動に活かされています。しかし、どんなに救護活動が進歩を遂げても、大災害時に救える命には限りがあります。
日赤は、東日本大震災をきっかけに、災害直後の応急対応に加え、防災・減災活動に社をあげて取り組むと決め、2017(平成29)年から防災教育事業を全国で開始しました。
東日本大震災時、防災教育を受けた子どもたちが率先して逃げたことが、多くの命を救うことにつながった釜石。しかし、これは決して奇跡ではありません。
日頃からの備えと行動によって一人でも多くの命が助かることが、日赤の願いです。
関東大震災から100年。聞こえてくるのは「明日に備えよ!」の声なのです。
 防災学習に取り組む青少年赤十字メンバー
防災学習に取り組む青少年赤十字メンバー
画像利用について
本サイト内の画像には著作権があります。画像を利用したい場合は、リンク・著作権についてより必ず申請ください。また他機関所蔵の画像・資料につきましては、別途所蔵機関への利用申請が必要となりますのでご注意ください。
関連所蔵品
※時代順にご紹介します。
{{ modalData['所蔵品名'] }}
-
{{ modalData['画像2'] }}
-
{{ modalData['画像3'] }}