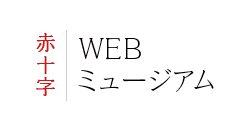特別企画

佐野常民生誕200年~日本赤十字社を創った男の素顔~

日本赤十字社の創設者 佐野常民は、幼少のころ佐賀(鍋島)藩医の養子になり、医者となる道を歩みます。頭脳明晰で努力家であった常民の勉強ぶりは、のちに長崎海軍伝習所(幕府の海軍士官養成所)でともに学んだ勝海舟が驚嘆するほどでした。
後年、常民は「吾輩は知恵も才能も何もない老翁だが、幸いに今日の位置にまで進んできたのはただただ勉強の一つである」と語るようになりました。そんな常民のことを「断られてもけなされても少しも頓着なく、二度が五度でもやるところまでやる」「ついには反対者も屈服する」「佐野さんに見込まれたらモウ仕方がない」とみな、とまどいながらも半ばあきらめと憧憬を込めて評しました。理想を掲げ、努力し続ける常民に共感せずにはいられなかったのです。
常民は、若くして佐賀藩の精煉方(理化学研究施設)で活躍し、明治政府においては大蔵卿や元老院議長を歴任するなど、多岐にわたる仕事をまかされました。赤十字は、それらの内のほんの一部であるように見えてくるほどです。しかし、常民にとって赤十字は、ほかの仕事とはあきらかに異なりました。危険をかえりみず戦地に足を運び、私財を投じ、人材の確保や物資調達に奔走し、なりふりかまわず、ときには泣きながら協力者を求めました。命が失われ、苦痛にあえぐ人々の惨状を見て見ぬふりができない、一人の人間としての常民の信念が浮かび上がってくるのです。日赤に遺されている記録からは、当時の日本に無かった革新的な人命救助の仕組みである赤十字を実現するには、「一人では何もできない」と考え、協力者を求めて行動し続けた姿が見えてきます。
幕末から明治を駆け抜けた一人の日本人が「赤十字」と出会い、日本赤十字社の創設と発展に尽力しました。日本における赤十字運動の充実・拡大に生涯を捧げた佐野常民の素顔に迫ります。
赤十字運動とは
- 赤十字運動は、国際的にはInternational Red Cross and Red Crescent Movement(国際赤十字・赤新月運動)と呼ばれ、世界192の国と地域で展開しています。
- 日本の赤十字運動は、毎年一定の資金を納める会員に支えられ、2022年現在、ボランティア114万人、青少年赤十字メンバー349万人、赤十字救急員等42万人、年間献血者505万人などに支えられ展開しています。
協力:佐賀市、大阪大学適塾記念センター、公益財団法人 日本美術協会
画像利用について
本サイト内の画像には著作権があります。画像を利用したい場合は、リンク・著作権についてより必ず申請ください。また他機関所蔵の画像・資料につきましては、別途所蔵機関への利用申請が必要となりますのでご注意ください。
佐野常民略記
1822(文政5)年12月28日 佐賀藩の藩士 下村充贇(みつよし)の五男として生まれる。幼名鱗三郎(りんざぶろう)
1867(慶応3)年 パリ万博に佐賀藩から派遣され赤十字を知る
1877(明治10)年5月1日 熊本県にて征討総督有栖川宮熾仁親王に博愛社設立請願書提出
1887(明治20)年5月20日 博愛社を日本赤十字社と改称。初代社長に就任
1902(明治35)年12月7日 東京の自邸で永眠。享年79歳
注目ポイント
-
 佐野常民
佐野常民
佐野常民は1822(文政5)年12月28日(太陽暦では1823年2月8日)、佐賀藩の財政を担う会計方の下村充贇(みつよし)の5男として誕生、鱗三郎(りんざぶろう)と名づけられました。出生地は有明海の河口近く、九州一の大河である筑後川が分岐した早津江川流域で、常民が幼少のころシーボルト台風により1万人以上の被害者を出した地域です。
常民は藩校弘道館で学ぶとすぐさま頭角を表し、満9歳で藩医の佐野常徴(つねみ)の養子となり、第9代藩主鍋島斉直から「栄寿」の名を授かります。実家の下村家で、父親の病気や長兄の死を経験した常民は、佐野家で藩医の後継者となるべく教育を受け、かの地で人の苦しみや自然の脅威を知り、忍耐強く、思いやりのある人格を形成していきました。
 佐賀県早津江川流域(佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館蔵)
佐賀県早津江川流域(佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館蔵)
-
 「扶氏医戒之略」(大阪大学適塾記念センター蔵)
「扶氏医戒之略」(大阪大学適塾記念センター蔵)
1846(弘化3)年、常民は佐賀藩主の鍋島直正から藩外留学を命じられ、広瀬元恭の時習堂(京都)、緒方洪庵の適塾(大阪)、華岡青洲の春林軒塾(和歌山)、伊東玄朴の象先堂塾(東京)など、当世一流の学者の下で最先端の蘭学、医学、化学を学びました。
とくに洪庵から学んだ「医戒」の一文「棄てて省みざるは人道に反す」という医者の倫理は常民の心に深く刻まれ、日本赤十字社創設の発想につながります。また、象先堂塾では常民が大病を患った際、師である玄朴の手厚い看病を受けました。これらの経験は、のちに常民が定めた「博愛社規則(社則)」や看護婦養成事業における精神的支柱「救護員十訓」につながりました。
九州に戻った常民は、藩主の命もあり、長崎で私塾を開校し、尊敬する恩師らの背中を追うように医者兼教育者としての道に乗りだしました。
 伊東玄朴(神埼市蔵)
伊東玄朴(神埼市蔵)
 緒方洪庵(大阪大学適塾記念センター蔵)
緒方洪庵(大阪大学適塾記念センター蔵)
-
 鍋島直正肖像写真(公益財団法人鍋島報效会蔵)
鍋島直正肖像写真(公益財団法人鍋島報效会蔵)
意気揚々と長崎で私塾を開いたばかりの常民(栄寿)を、藩主鍋島直正は佐賀に呼び戻し、侍になり栄寿左衛門と名乗るよう命じます。医者として剃髪していた常民は、髪が生えそろうまでカツラをつけて出仕しました。
直正は、幕府の長崎警備を担う藩主として、海防強化と科学技術向上のために人材を集め育成しようとしたのです。常民は精煉方(理化学研究施設)で直正の厚い信頼に応え、日本初の蒸気船と蒸気機関車のひな形を完成させ、アームストロング砲の開発にもかかわりました。1855(安政2)年には幕府の長崎海軍伝習所で外国人教師から航海術、造船技術、蒸気機関、数学などを学び、佐賀に戻ると蒸気船淩風丸建造の指揮をとり、海軍士官養成も行いました。
国防の最前線で大型蒸気船や蒸気機関車の開発にかかわった常民の経験は、後年、日赤が病院船や病院列車を活用し、海を越えて人命を救う行動につながりました。
-
 赤十字パビリオン(“L'Exposition universelle de 1867 : illustrée”)
赤十字パビリオン(“L'Exposition universelle de 1867 : illustrée”)
1867(慶応3)年のパリ万国博覧会に出展した佐賀藩は派遣員として常民を含む5人を抜擢し、有田焼などの佐賀の特産品を世界に売り込むことと、欧州の最先端技術を学び軍艦を購入することを命じました。
万博会場には、誕生したばかりの国際赤十字がパビリオンを設け、医療器具を展示するとともに各国の来館者に対して、ジュネーブ条約への加入を訴えていました。これが常民と「赤十字」の出会いです。常民は、敵味方関係無く救護するための国際条約と活動の仕組みに衝撃を受けました。
パリでは、幕府から派遣された高松凌雲(適塾で学び、箱館戦争で敵味方の別なく負傷者救護を行った)や、のちに日赤の支援者となる渋沢栄一、アレクサンダー・シーボルトなどと出会いました。
 佐賀藩派遣団・中央常民(『仏国行路記』より)
佐賀藩派遣団・中央常民(『仏国行路記』より)
-
 常民の演説原稿に「文明開化」の文字
常民の演説原稿に「文明開化」の文字
常民がパリから帰国すると、徳川幕府はすでに倒れ明治政府が誕生していました。常民は1870(明治3)年、兵部省(軍務)、続いて工部省(鉄道、電信など)に出仕。1873(明治6)年には、政府からウィーン万国博覧会の事務副総裁(総裁は大隈重信)に任じられ、ふたたびヨーロッパに旅立ちました。常民は渡航先で見聞した最先端技術を、報告書『澳国博覧会参同紀要』(平山成信、田中芳男編)にまとめ政府に提出。日本の近代化に貢献します。
また常民は、万博での各国の展示に赤十字活動が反映されているのを見て、ヨーロッパにおける赤十字運動の急速な発展を実感しました。この思いは、のちに常民が語った「文明開化といえば人はみな法律や精密な機械ができることをいうが、赤十字のような活動が盛んになることこそが文明開化の証である」(1882(明治15)年博愛社社員総会演説)の言葉に表れています。
後年、ウィーン万博に同行した人々は日本赤十字社の社員(支援者)となりました。
 ウィーン万博派遣団(有田町歴史民俗資料館蔵)
ウィーン万博派遣団(有田町歴史民俗資料館蔵)
 ウィーン滞在時の常民(『日本赤十字社社長伯爵佐野常民伝』)
ウィーン滞在時の常民(『日本赤十字社社長伯爵佐野常民伝』)
-
 博愛社設立許可の図
博愛社設立許可の図
常民がヨーロッパに滞在中の1874(明治7)年、日本では佐賀戦争が勃発。同郷の多くの士族が傷つき倒れました。外国にいた常民は、悲惨な最期を遂げた友らに対して救う術もなく、涙するしかありませんでした。
3年後の1877(明治10)年、最後にして最大の内戦となった西郷隆盛率いる薩摩軍と日本政府軍の戦いが起きました。日々報道される多くの若者の悲惨な死に胸を痛めた常民は「敵味方なく救う」救護組織の設立を目指します。岩倉具視に相談し、元老院議官を務めていた大給恒とともに行動し、多くの人々の心を動かしました。常民は有志らの支えによって、征討総督の有栖川宮熾仁親王に博愛社と名づけた救護組織の設立請願書を提出し許可を得ました。これが日本赤十字社の始まりです。
 設立請願書
設立請願書
-
 昭憲皇太后
昭憲皇太后
戦時救護のために設立された博愛社は、西南戦争が終結すると、存続が危ぶまれました。そのような状況下、初代総長小松宮彰仁親王は、第1回社員総会で西南戦争での救護活動を称賛し、博愛社の永続的な発展の基盤を築くよう参加者を激励しました。小松宮親王は弱小組織だった博愛社のほとんどの決裁にかかわり、支援者への報告も自ら行いました。
さらに皇后(のちの昭憲皇太后)からの毎年300円の寄付が決定。1886(明治19)年には明治天皇皇后の支援によって最初の赤十字病院が設立。1888(明治21)年の磐梯山噴火の際には、皇后の内旨を受け世界にさきがけ日赤の災害救護が始まりました。
また博愛社の設立を許可した有栖川宮熾仁親王も、第2代総長として活動を支えます。
このように、皇室との縁ができた日本赤十字社ですが、常民も日赤社長の立場で宮中顧問官となり、皇族の外交上の儀典などを支えました。
*小松宮彰仁親王(こまつのみやあきひと)は、時代により仁和寺宮嘉彰親王(にんなじのみやよしあき)、東伏見宮嘉彰親王(ひがしふしみのみやよしあき)とも称しました。
 小松宮彰仁親王
小松宮彰仁親王
 有栖川宮熾仁親王
有栖川宮熾仁親王
-
 1880(明治13)年1月の加入者名簿(「博愛社報告原稿」より)
1880(明治13)年1月の加入者名簿(「博愛社報告原稿」より)
博愛社は設立当初から社員(支援者)からの社費(会費)によって運営することとされました。大給は早速親戚縁者に、常民は同郷や遊学時の知人、渋沢栄一などパリ並びにウィーン万博の縁者のところに足しげく通って西南戦争の経験を伝え、社員となるよう勧誘します。常民はドイツ留学中の長男常實を1880(明治13)年に病気で失った悲しい経験から、若者の死について語るとき人目をはばからず泣いたと言われます。また、寄付を断られても屈辱的なあつかいを受けてもめげない姿は、大給から「なまこ」と呼ばれるほどでした。
同郷の後輩である大隈重信は、常民について「西南戦争時に初めて赤十字思想を提唱したときは、日本中だれ一人として耳を傾けるものもおらず、それを知る人もいなかったが、(常民が)誠実かつ熱心に政府あるいは民間の間を遊説し、今日においては巨大な組織を作り上げ、欧米列強に対しても文明国と認めさせることに成功した」と語りました。
常民は終生、赤十字運動に私財を投じ、社員の勧誘を続けます。
*日本赤十字社では、毎年一定額の社費(活動資金)を納入してくださる方を会員(当時は社員)と呼び、実務を担う有給のスタッフを職員と呼んでいます。
 大隈重信(近代日本人の肖像 歴代首相等写真 憲政資料室収集文書1142)
大隈重信(近代日本人の肖像 歴代首相等写真 憲政資料室収集文書1142)
 渋沢栄一(『渋沢栄一伝記資料』別巻第10,p.113,「渋沢栄一フォトグラフ」)
渋沢栄一(『渋沢栄一伝記資料』別巻第10,p.113,「渋沢栄一フォトグラフ」)
-
 篤志看護婦人会発起人名簿
篤志看護婦人会発起人名簿
1887(明治20)年に誕生した日赤の最初のボランティア組織「篤志看護婦人会」の発起人代表となったのは、有栖川宮熾仁親王妃董子(ただこ)でした。新潟新発田藩主の姫で戊辰戦争の悲劇を知る彼女を中心に女性たちが集います。
女性による活動やボランティア組織を立ち上げる発想は、もともと国際赤十字の創始者であるアンリー・デュナンによるものですが、当時の日本では革新的でした。常民は、ボランティア組織の設立集会への案内状を最後の佐賀藩主鍋島直大の妻栄子や大山捨松などに送付し、常民の妻駒子も会の発起人として参加しました。彼女たちは、高貴な身分でありながら自ら率先して救護活動を支えるために包帯を作成したり、救護や看護の知識を学んだりすることで、看護婦の社会的地位を高めることに貢献しました。会員数は多いときで10万人におよびました。
 有栖川宮熾仁親王妃董子(松戸市戸定歴史館蔵)
有栖川宮熾仁親王妃董子(松戸市戸定歴史館蔵)
 鍋島栄子(公益財団法人鍋島報效会蔵)
鍋島栄子(公益財団法人鍋島報效会蔵)
-
 1903(明治36)年「日本赤十字」第121号
1903(明治36)年「日本赤十字」第121号
赤十字運動の実現のために奔走する常民を評して、親しい人たちは口々に以下のように語りました。
ともに博愛社を立ち上げた大給は常民を「なまこ」のようだと評し、それを周囲は「悪い評のようだが、その主旨はすこぶる妙と思ふ。叩いても、ひねっても、折っても、引張っても少しも変わらない…伯の性質をよく穿ったものだ」と言っています。
同様に伊藤博文は「佐野に会うや、くどくどと言葉が次々に出てきて、聞くのが嫌になるが、後から考えるとそれは物事の本質を言い当てており、敬服せざるを得ない」と語ります。
小松宮侍従だった高崎正風は、「とうとう六度まで自ら来て説きつけられたから、私も終いに根気負けをして入社した(*支援者を意味する社員になったという意)。…東久世伯にこの話をすると、東久世には七度、だれは三度、かれには四度というようなことばかり」と懐古しています。
常民と大給のたった2人から始まった赤十字運動が、日本中を巻き込む大きなうねりとなっていったのは、常民のあきらめない姿勢によるものと言えるでしょう。
 大給恒
大給恒
 伊藤博文(近代日本人の肖像 歴代首相等写真 憲政資料室収集文書1142)
伊藤博文(近代日本人の肖像 歴代首相等写真 憲政資料室収集文書1142)
-
 日赤本社にあった佐野常民立像(「日本赤十字」第101号掲載)
日赤本社にあった佐野常民立像(「日本赤十字」第101号掲載)
1901(明治34)年7月11日、常民の立像の除幕式が日本赤十字社本社で行われ、総長の小松宮親王をはじめ300人以上の参列者が常民とその家族を囲みました。 作者の鈴木長吉は像の制作にあたり「佐野さんのためなら全力を尽くし、費用も実費だけで結構です」と申し出ました。
常民は、1879(明治12)年に「龍池会」(現在の公益財団法人日本美術協会)を創設し、初代会頭でもあったため、日本を代表する金工家の鈴木とも親交があったのです。
日赤の立像は第2次世界大戦時の金属類回収令によって手放したため、残念ながら現存しません。
しかし、鈴木が制作した別の常民の胸像が存在するのです。これは日本美術協会が大切に保管し、現在は上野の森美術館が所蔵しています。
常民は芸術の振興も赤十字運動の浸透と同様に文明開化の証と考えていました。それを象徴するのが、鈴木長吉作の2つの常民像なのです。
*鈴木長吉(1848-1919)は、明治~大正期の金工家。「十二の鷹」(東京国立近代美術館蔵)は重要文化財。
 佐野常民ミニチュア陶像(博多織元、松井人形部)幻の立像を模して制作
佐野常民ミニチュア陶像(博多織元、松井人形部)幻の立像を模して制作
 佐野常民像 鈴木長吉 上野の森美術館蔵
佐野常民像 鈴木長吉 上野の森美術館蔵
-
 晩年の佐野常民
晩年の佐野常民
常民は肝臓を患って以降、日赤社長を続けながらも養生を余儀なくされました。また、後年馬車の事故による大けがやリウマチにより、杖が欠かせない生活となりました。しかし、常民は老いてもなお赤十字のために働き続けました。
記録には、つぎのような記述があります。出張先の沿道で常民を歓迎する人々を見かけると、雨の中でも人力車から降り「頓着なく濡れ鼠の姿で一々挨拶されるので、同行者即ち知事書記官、警部長や郡長その他の社員等も一々降りざるを得ない次第で随分迷惑らしく見える」が、本人は構わず、送迎者の情に感動して涙を流しながら挨拶しているというのです。また、どこでも同じ演説をくり返し、毎回涙する姿も描かれています。「(佐野)伯は全くの情の人である」と称された常民の人物像が浮かびます。
1902(明治35)年12月7日に常民が79歳で亡くなったとき、日本赤十字社の社員は80万人となっていました。葬儀には駐日ドイツ公使などの外国人を含む3000人が参列しました。
 佐野常民葬儀(佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館蔵)
佐野常民葬儀(佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館蔵)
-
 東日本大震災 対策に追われる救護班
東日本大震災 対策に追われる救護班
常民が洪庵から学んだ「棄てて省みざるは人道に反す」という教えや、常民がたびたび口にした「惻隠の情」、すなわち他者へのいたわりや人を救いたいという、だれもが生まれ持った心は、常民によって日本赤十字社という人命救助を目的とする革新的な仕組みになりました。人の命と健康、尊厳を守るための法が整備され、人員が訓練され、さまざまな予防対策も行われるようになりました。
常民はその生涯をかけて、身をもって「赤十字は行動である」と示しました。日赤の活動は現在も会員(かつて社員と呼んだ)に支えられ、ボランティア114万人、青少年赤十字メンバー約349万人、赤十字救急員約42万人、年間献血者505万人、職員6.8万人に上ります。常民が育んだ「赤十字」のバトンは今を生きる私達に託されています。
 バングラデシュの難民キャンプ© Atsushi Shibuya/JRCS
バングラデシュの難民キャンプ© Atsushi Shibuya/JRCS
 COVID-19 クルーズ船に向かう救護班
COVID-19 クルーズ船に向かう救護班
関連所蔵品
※時代順にご紹介します。